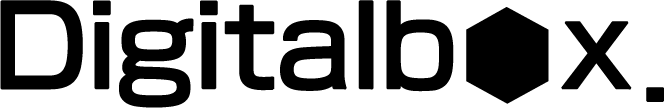製造業は、1つの製品を作るために数十から数百の工程を渡る必要があります。それにも関わらず、日々の業務に追われるうちに、製造業のマニュアルの作成や管理は後回しになりがちです。製造業の現場で使いやすいマニュアルは、どういったものでしょうか。この記事では、現場で求められる情報や工夫、書き方を紹介します。
【製造業のマニュアルを整えるとできること】
〇 業務の品質が統一できる
〇 従業員の欠員に対応できるようになる
〇 労災の予防になる
連載「職種別で解説!業務マニュアルの改善ヒント」
1. スムーズな引継ぎでミス予防!「事務職」業務マニュアルの改善指針
2. 早期離職を予防!「コールセンター」業務マニュアルの改善指針
3. 業務の品質を統一!「製造業」業務マニュアルの改善指針
4. 属人化を改善!「コンタクトセンター」業務マニュアルの改善指針
5. 全体感を把握して一丸で働く!「EC業界」業務マニュアルの改善指針
6. 現場教育を効率化!「飲食業」業務マニュアルの改善指針
7. 業務の効率化を進める!「経理部」業務マニュアルの改善指針
製造業の実態
業務マニュアルは、現場にある課題を解決できるものでなくてはなりません。「製造業」にはどのような特徴があり、どのような課題を抱えているのでしょうか。
製造業の特徴と課題
品質の差が出やすい
製造業では各工程を担当する作業員によって技術力が異なります。多くの製造現場では1秒でも早く作業に慣れるために口頭・実演での教育を一般化していますが、コツはすぐつかめるものでもありません。どうしても新人とベテランとでは出来上がりにも差が出やすいのが現実です。
工程数が多い
製造の現場では、数百にわたる工程があります。「各作業員がどのような手順・目的で作業をしているのか」を把握することは重要です。しかし、特に現場を仕切る管理職の場合、数百にわたる工程すべてを経験するのはほぼ不可能です。チーム全体の作業を把握しづらい環境なのです。また、「自分と前後の工程だけを把握していれば良い」と考える作業員もまだまだ多くいます。
危険な業務がある
製造業では、作業内容によって危険を強いられる場面も多くあります。場合によっては、取返しのつかない事態になることすらあります。労災は現場だけでなく企業全体の損失です。そういった事態にならないよう、労災を防止するための注意喚起は必須です。
製造業のマニュアルの失敗
上記のような現場の事情を踏まえ、近年では、マニュアルが導入された製造業も多くなりました。しかし、体制の古い企業では、いまだに管理・運用がずさんなケースも少なくありません。ここでは、製造業で実際に起こりがちなマニュアルの失敗例を紹介します。
理解しづらい
製造業におけるマニュアルは、数十~数百にもわたる工程を記載するので情報量が膨大です。そのため、マニュアルの物量を抑えるために1ページごとの情報量が肥大化するケースも多くあります。そのせいで理解しづらいものになるのです。
読み手が理解しづらいマニュアルは、閲覧に時間がかかるだけではありません。作業内容への理解が曖昧になるため、トラブルのリスクが増加する危険性もあります。
使いづらい
マニュアルの数が膨大になると、閲覧したい情報を見つけるのにも時間が必要です。情報を探しているうちに似たような作業工程を発見し、間違った情報をインプットしてしまう、といったリスクも高くなります。閲覧者がスムーズに情報を得るための配慮は必要です。
情報が古い
より安全で効率的な作業が発案された場合や、新しい工具や機材が導入される際には、作業内容が更新されます。マニュアルの情報が古いままだと、効果的な提案が活かされません。さらに、過去のトラブルが再発する危険性もあります。
また、マニュアルと実際の現場に置かれている工具や機材がリンクしなければ、閲覧者の混乱を招いてしまうでしょう。現場の効率化を目指すには、マニュアルの情報を更新し続けることも重要です。
現場が欲しい情報と工夫
「製造業」独自の課題を解決し、使われる業務マニュアルにするためにはどうすればよいのでしょうか。「製造業」の業務マニュアルには次の項目が必要です。
| 業務の品質を統一したい |
|---|
| 分かりやすい業務の判断基準 |
| 欠員にも対応できるようにしたい |
|---|
| 自然と入ってくる業務の全体感 |
| 労災を防止したい |
|---|
| 目につく危険箇所の喚起 |
「理解しやすい」「使いやすい」「情報が新しい」に気を付けてこれらを書くことで、理想の「製造業」業務マニュアルになるのです。なお、業務マニュアルの作り方については、下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご確認ください。
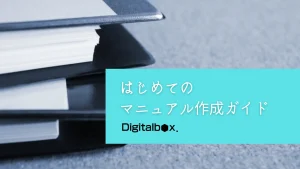
分かりやすい業務の判断基準
作業の担当者によって、出来上がりに違いができてしまうものです。しかし、現場ではスケジュールの都合などで別の作業員が担当せざるを得ないこともあります。そこで完成した製品にムラがあってはなりません。出来上がりの差やタイムラグが生じないためにも、業務で求められる基準の分かりやすさは重要です。
膨大な情報量を収めようとして、1ページごとに記載される情報量が肥大化するケースは多い。例えば、なるべく多くの情報を盛り込むために、写真を使わず文章だけを羅列し、文字を小さくするといった方法である。
理解しづらいマニュアルは、閲覧に時間がかかり、トラブルに繋がる危険性も増加します。視覚的に分かりやすくすることが重要です。
| 項目 |
|---|
| ・作業時の体勢 ・必要な人員数 ・作業分担 ・出来上がりのOK例、NG例 ・チェックシート |
| 工夫 |
|---|
| ・音やにおいなど、五感で判断できる情報を書く ・文字を大きく書く ・写真、映像、音声を交えて書く |
なお、マニュアルを作成する時には、その業務のエキスパートが行う方法を手順に落とし込むと良い。
作成していると、作業内容を詳細に書きとめることで、無駄な部分を発見することもあるでしょう。マニュアルの作成時に作業内容を1つずつチェックするため、より効率的な作業内容を発案することもあります。こういった無駄の修正をおろそかにすると、管理・運用が曖昧になり、業務内容が改善されません。必ず良い方法を確定し、書きとめましょう。
自然と入ってくる業務の全体感
製造業において、各作業員がどのような手順・目的で作業をしているのかの把握は重要です。マニュアルを活用することでチーム全体の作業内容が把握できれば、欠員やトラブルの発生時にスムーズに対処できるというメリットがあります。
なお、マニュアルの数が膨大になると、自分の閲覧したい情報を見つけるのに時間を要するだけでなく、似たような作業工程を発見することで間違った情報をインプットしてしまうリスクも高くなります。閲覧したい工程を絞りやすくするため工程ごとをグループ分けするなどの工夫も重要です。
また、冊子型マニュアルの場合はインデックスシールなどを活用すると良いでしょう。マニュアルを開く前に閲覧したい情報のおおよその場所を把握できるようになるなど、スムーズな情報取得に繋がります。
| 項目 |
|---|
| ・目次 ・工程ごとのグループ分け ・業務ごとの目的 |
| 工夫 |
|---|
| ・工程ごとの色分けをする ・インデックスシールを活用する(冊子型のマニュアル) |
目につく危険箇所の喚起
労災を避けるためにも、危険箇所はしっかりと喚起しなくてはなりません。テキスト型マニュアルの場合、写真や強調文字などを使えば、危険な作業箇所や安全な動作を分かりやすく伝えられます。また、過去に発生した労災を記録することで、二度と同じトラブルを起こさないための注意喚起を行うものも多くあります。
より安全で効率的な作業が発案された場合や、新しい工具や機材が導入される際に、作業内容は更新されます。マニュアルの情報が古いままだと、効果的な提案が活かされないだけでなく、過去に起きたトラブルの誘発にも繋がります。危険箇所を減らすためにも、マニュアルの情報を更新し続けることも重要です。
| 項目 |
|---|
| ・異常時の対応方法 ・OK・NG例 ・過去の労災例 |
| 工夫 |
|---|
| ・統一された注意喚起マークを付ける ・太文字、アンダーライン、色使いで目立つようにする ・画像で伝える ・定期的にマニュアルを確認、更新する |
なお、〈マニュアル作成ツール〉を使ってマニュアルを管理すれば、更新も簡単にできるようになります。
製造業のマニュアルの書き方
「製造業」の場合、マニュアルの閲覧者のほとんどは作業員で、作業を一旦中断して急いで確認している場合が多いでしょう。閲覧の時間を短縮するには、誰が見ても理解しやすく使いやすいマニュアルを作成しなければなりません。それでは、どのようにマニュアルを書けばよいのでしょうか
使えるライティングテクニック
分かりやすい文章を書く 誤読を防いで書く 注意喚起
難しい専門用語や言い回しはなるべく避け、簡潔で分かりやすい言葉で記載するのがベストである。
・指示語を避ける
✕「それを引っ張ります」
〇「レバーを引っ張ります」
・箇条書きで書く
✕「ブザーが鳴ったら、庫内の消火とランプの消灯を確認してください」
〇「ブザーが鳴ったら、次のことを確認してください
・庫内の消火
・ランプの消灯」
・「~し」「~り」で文章を繋がず、文章を分ける
✕「取っ手を右手で固定し、左手でフタをします。」
〇「1.取っ手を右手で固定します。
2.左手でフタをします。」
・修飾語は、就職する言葉の近くに置く
✕「目立つ黄色のスイッチ」
〇「黄い色をした、目立つスイッチ」
・数値を使って具体的に書く
✕「数センチ空けて並べてください」
〇「3~5センチの間隔をあけて、並べてください」
・「気を付けてください」は、本当に必要な箇所で使う
✕「扉は重たいので気を付けてください。
庫内の箱は熱くなっています。火傷しないように気を付けてください。」
〇「扉は重くなっています。
庫内の箱は熱くなっています。火傷しないように気を付けてください。」
【製造業のマニュアルを整えるポイント】
〇 「このマニュアルで何を改善するのか?」作成の目的を意識する
〇 「このマニュアルで課題が解決できるか?」を確認しながら作成する
〇 危険箇所があれば必ず注意喚起がされているかを確認する¥